サッカー観戦中、ふと気になるピッチの芝生。日本のスタジアムとヨーロッパのスタジアムでは、何となく芝の色が違うように感じませんか?鮮やかな緑色のヨーロッパのピッチに対し、日本のピッチは少し色が薄い気がする…。
この記事では、そんな素朴な疑問から、ピッチの芝生の模様の作り方、スタジアム建設の背景にある違いまで、サッカーのピッチに関するあらゆる謎を徹底的に解き明かします!これを読めば、次にスタジアムで観戦する時、あるいはテレビで試合を見る時の見方が変わるかもしれませんよ。
日本とヨーロッパのスタジアム建設における根本的な違い
ピッチの環境について語る前に、実はスタジアムが建設される段階から、日本とヨーロッパでは大きな違いが存在します。それは、スタジアムの所有者です。
ヨーロッパの多くの強豪クラブは、莫大な資金力を持っているため、自分たちの専用スタジアムを所有しているケースが少なくありません。彼らは、選手が最高のパフォーマンスを発揮できるピッチ環境を追求し、それがひいてはチームの勝利、そして収益にも繋がると考えてスタジアムづくりに力を入れています。
一方、日本では、国や都道府県などの行政がスタジアムを所有しているケースが多く見られます。そのため、スタジアムの運営においては、興行収入だけでなく、公共性や他のスポーツイベントでの利用なども考慮される必要があります。
最近の日本のスタジアムでは、屋根に光を透過するガラスを採用するなどの工夫が見られますが、少し前に建設されたスタジアムでは、必ずしも芝生の育成環境が最優先に考えられていなかったかもしれません。対照的に、ヨーロッパのクラブチームは、「いかに良い芝生を育てるか」という視点からスタジアムの設計に取り組むことが多いようです。
どちらが良い悪いという話ではありません。それぞれの国の文化やスポーツを取り巻く環境が、スタジアムのあり方にも大きく影響していると言えるでしょう。
ピッチの謎を解明!あの美しい芝生の模様はどうやってできるの?
さて、いよいよピッチそのものに目を向けていきましょう。皆さんがサッカー中継などで目にするピッチには、必ずと言っていいほど縦縞模様が入っていますよね。濃い緑と薄い緑のコントラストが美しいこの模様は、一体どのようにして作られているのでしょうか?
実はこの模様、芝刈りの際にできる副産物なのです。芝生は、刈られる方向に寝る性質があります。奥に向かって刈られた芝は光を反射して白っぽく見え、手前に向かって刈られた芝は影になって黒っぽく見える。この芝の向きの違いが、あのストライプ模様を作り出しているのです。
模様をつける目的は、見た目の美しさだけでなく、芝生が常に同じ方向に寝てしまうのを防ぐという効果もあります。昔は、斜めに刈り込んだり、複雑な模様を描くスタジアムもありましたが、2017年頃から、副審がオフサイドラインを判定しにくいといった理由で、現在の縦縞模様に落ち着いてきました。
観客やグラウンドキーパーからすると、個性的な模様は魅力的ですが、プレーの公平性を考えると、現在の形が最適なのかもしれませんね。
なぜ違う?日本とヨーロッパの芝生の色
サッカーファンなら一度は疑問に思ったことがあるかもしれません。なぜプレミアリーグなどのヨーロッパサッカーのピッチは、Jリーグの夏場のピッチよりも緑色が濃いのでしょうか?
これは、日本の芝生が汚いとか、管理が悪いというわけではありません。単純に芝生の品種が違うのです。
ヨーロッパで主に使われているのは、寒地型と呼ばれる、低温環境でも生育に適した品種です。一方、日本は高温多湿な夏があるため、暑さに強い暖地型の芝生が広く使われています。夏芝冬芝という呼び方をする場合もあります。
この品種の違いは、日本の特有の気候、つまり大きな寒暖差が大きく影響しています。ヨーロッパは日本ほど極端に気温が上がることが少ない一方(近年の異常気象は除く)、日本は冬には氷点近くまで下がり、夏には40℃近くになることもあります。
もしヨーロッパでよく見られる寒地型の芝を日本で育てようとすると、夏の暑さに耐えきれず、枯れてしまう可能性が高いのです。そのため、日本では暖地型の芝をベースとして使用しています。
そして寒地型の芝生の多くは、暖地型の芝生よりも色が濃いため、ヨーロッパのピッチの色は濃く見えると言わけです。
日本のピッチが一年中緑を保つ秘密 – オーバーシーディングという技術
ここで新たな疑問が生まれるはずです。「暖地型の芝を使う日本のスタジアムは、なぜ冬でも緑色を保っているのだろう?」と。
その答えは、オーバーシーディングという特別な技術にあります。これは、冬が来る前に、暖地型の芝生の上に寒地型の芝生の種を撒くという方法です。
寒さに強い寒地型の芝は、冬の間も緑を保ち、春になると暖かくなるにつれて成長します。一方、暖地型の芝は冬に休眠しますが、夏になると再び成長を始めます。このように、二つの異なる品種の芝生を組み合わせることで、日本のピッチは一年を通して緑豊かな状態を維持しているのです。
暖地型と寒地型の大きな違いの一つが、先ほどもお伝えしたように見た目の色の濃さです。以下の写真は、あるグラウンドの同じ場所の夏場の芝生と冬場の芝生を比較したものです。


品種が違うだけで、これほどまでに色が異なるのは一目瞭然ですよね。つまり、日本のピッチが冬場に濃い緑色に見えるのは、寒地型の芝がメインになっているからなのです。そして、春から秋にかけて色が薄く見える時期があるのは、暖地型の芝が中心になっているためです。
この品種の違いとオーバーシーディングという技術こそが、ヨーロッパと日本のピッチの色の違いであり、日本ならではの常緑を保つための知恵と言えるでしょう。ちなみに、夏場になると、寒地型の芝は暖地型にとって生育の邪魔になるため、積極的に枯らすような管理が行われます。
もちろん、日本でも寒地型の芝だけで一年中管理しているスタジアムも存在します。その方法としては、打ち水のように頻繁に水を撒いて地温を下げる、あるいは地面の中に冷却用のパイプを通して冷水を循環させるなどの工夫が行われています。これらの方法は管理に手間とコストがかかるため、限られたスタジアムで採用されています。
重要なのは、日本のピッチの色が薄いからといって、芝生の状態が悪いわけではないということです。それは、気候に合わせた品種選びと、一年中美しいピッチを維持するための努力の結果なのです。
屋根付きスタジアムでの芝生管理 – 日照不足との戦い
近年増えている屋根付きのスタジアムでは、芝生の管理において新たな課題が生まれます。それは、日照不足です。
植物である芝生にとって、日光は健康的な成長に不可欠です。光が不足すると、芝の葉は細くひょろひょろになり、根が十分に張らず、弱い芝生になってしまいます。その結果、芝生は剥がれやすくなり、ピッチ環境は悪化してしまいます。
この問題を解決するために導入されているのが、グローライトと呼ばれる人工照明です。これは、強い光を芝生に照射することで、太陽光が当たっていると錯覚させ、光合成を促すものです。
ヨーロッパのスタジアムでは、多くのグローライトがピッチ上に設置されている光景を目にすることがありますが、一台あたりの価格が高額なため、日本ではまだ導入が進んでいないのが現状です。また、管理維持費や消費電力も大きいため、小規模なスタジアムでの導入は慎重に検討する必要があります。
まとめ – ピッチへの理解を深めて、もっとサッカーを楽しもう!
この記事では、日本のピッチとヨーロッパのピッチの違い、芝生の模様の秘密、そしてスタジアム建設の背景にある考え方の違いについて解説しました。
- 日本とヨーロッパでは、スタジアムの所有形態や建設の目的が異なる。
- ピッチの縦縞模様は、芝刈りの方向によって生まれる。
- 日本とヨーロッパで芝生の色が違うのは、気候に合わせた品種の違いによるもの。
- 日本ではオーバーシーディングという技術で一年中緑のピッチを維持している。
- 屋根付きスタジアムでは、グローライトなどの人工照明で芝生の育成をサポートしている。
これらの知識を持つことで、これまで何気なく見ていたピッチの風景も、より深く理解できるようになるはずです。次にサッカー観戦をする際には、ぜひピッチの芝生にも注目してみてください。きっと新たな発見があるはずです!
そんなグラウンドキーパー、グラウンズパーソンを目指したくなった方へ
ここでは芝生管理専門の求人サイトを設けています。
ぜひ自分の芝生管理者としての未来を切り開いてみてくださいね!





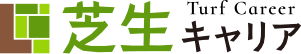
コメント